
06 Mar 2002
■バヌアツには各国からボランティアの人びとがやってくる。教育と医療と地域開発が彼らの職種の三本柱である。

■首都の宿に泊まっている時にニュージーランドからきたボランティア女性と話をする機会があった。日本からのボランティアはたいてい20代の若者が中心であるが、海外からのボランティアはさまざまな年齢層にわたり、彼女もまた50代ですでに十分なキャリアをもった教師であった。
■地域に密着しながら生活をするボランティアたちの経験を聞くのは面白い。人類学者の視点と彼らの視点は重なり合うことが多いからだ。そしてこのニュージーランドの女性との話は特に楽しいものだった。
■彼女は、ボランティアの経験をとおしてメラネシア人のものの理解の仕方に独特なものがあるのではないかと感じていた。そして西欧式の教育システムにはどこか無理があるのではないかというのだ。
■彼女の実感を簡単に説明すると、バヌアツの子どもたちは教えたことを丸ごと覚えるのは得意であるが、概念化して論理的に組み立てるような作業に入るととたんに行き詰まってしまうというものだ。
■「これってなんだろう」彼女は問い掛ける。包括的で非統合的な学習法。「つまりそれはホーリスティックな理解なのでしょうか」私は言葉を選んで返す。「なるほどホーリスティックね」彼女はうなずく。
■私にもその感覚はよく分かった。そして私は彼女に、日本語をテープレコーダーのように完璧に覚えてしまったソロモンの若い語り部の話をした( ソロモンタイム「モダニズム批判」 参照のこと)。人間がものごとを理解する時にはおそらくさまざまな過程があるはずだが、近代教育ではその中でとくに分析と統合というアプローチに偏りすぎているのではないかと指摘した。「読み書きそろばん」といったリテラシーにおいて、文字や数字というのはまさに概念のアナライズ・シンセサイズ操作の象徴みたいなものである。
■彼女はニュージーランド先住民であるマオリの人びとの教育にたずさわったこともあり、そのときもやはり同じような印象をもったという。そしてニュージーランドでは彼らの伝統的な教育システムを再検討しはじめていると語った。
■私はメラネシアの人々の知的能力が劣っているとはまったく思っていない。たとえば絶海の孤島に島流しにあって生き残れるのは私ではなくまちがいなく彼らである。複雑な人間関係や多様な自然環境の中で生きていくときの彼らの卓越した能力には、何度も驚かされてきた。実際、村での暮らしの中で私の持っている能力などほとんどなんの役にも立たない。
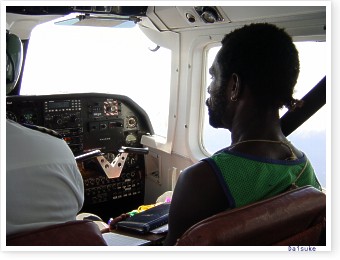
■それよりも気になるのは彼らの理解の仕方である。
■別の人からこんな話も聞いた。バヌアツの人にコンピュータを教えているときに、あるアイコンをクリックするようにいった。そのアイコンはたまたま画面の右上にあった。するとそれを隣で見ていた人が、自分も同じようなことをしようと画面の右上をクリックしようとする。しかし彼の画面では同じアイコンが右下にあった。それを見ていて、彼らにはシンボル操作ができないのではないかと感じたという。
■伝統社会の中で変化にとむ象徴体系をつくり上げてきた彼らが単純なシンボルを操作できないとはとても思えない。しかし物事を理解する過程のどここかに根本的な違いがあるのではないかという指摘には同意できる。それをどう呼んでいいのかうまく説明できないないが、やはりある種のホーリスティック(全的)な世界理解をそこに感じる。

■2月15日。私はタナ島にいた。おりしもその日は年に一度ジョンフルムという聖者がが莫大な富を持ってこの地を訪れるとされている特別な日であった。ジョンフルムの再来を信じる人々がスルファベイという海岸に集まり一昼夜踊りつづけた。
(タナ島には定期的に溶岩を吹きあげる活火山があり、そのふもとが彼らの聖地 である。地鳴りが鳴り響く中、夜を徹して繰り広げられる風景は、まさに「土人 の踊りと火山」という冒険ダン吉にはじまり手塚治虫やモスラに引き継がれた、 南洋のモチーフの原点を目の当たりにする思いであった)
■第二次世界大戦前後にメラネシア各地でさまざまなカーゴカルト(積荷信仰)が生まれた。不思議なことにこれらの信仰では、地理的にはなれた島々で独自の教義が同時多発的に発生している。タナ島ではジョンフルムと称する白人が大量の積荷を持って島に現れるというすじがきで信仰が形成された。
■こうした積荷信仰の背景には、第二次世界大戦のときにアメリカ軍が大量の物資を持って各地の島に現れ、戦闘終了後にそれをそのままおいて帰ったという歴史的な事実がある。タナ島の場合は座礁した輸送船がそのはじまりであると言われている。しかしその一回きりの出来事を、信仰にまで高めてしまう彼らの世界観とはいったいなんだろうか。
■童謡「待ちぼうけ」の元になった守株の故事は、たまたま切株にウサギがぶつかって死んだのを目撃した農夫が、それに気をよくして農作業をやめてしまい次のウサギが株にぶつかるのをひたすら待ちつづけるという笑い話である。メラネシアのカーゴカルトを見ているとこの話が笑えなくなる。
■いうまでもなく現在の彼らは、第二次世界大戦とアメリカ軍の関係を知っている。すでに教育やラジオによってわれわれと同じような知識をもち、国際的な政治状況についても決して無知ではない。なぜあの時積荷がきたのかという因果関係はわかっているのだ。わかっていながら、必ずまたそれは来ると信じるのである。
■しかもこのカーゴカルトは蒙昧な土着信仰などではなく、キリスト教の影響を強くうけた新興宗教であり、植民地からの独立を志向する前衛的な民族主義運動につながっていったのである。

■最もはやく外来文化を受容しそれを希求したカーゴカルトのメンバーたちが、不思議なことに最も強烈に伝統社会への回帰を訴えカスタム(昔ながら)の暮らしを守ろうとするというのは、なんとも理解しがたい現象といえる。
■海の向こうからやってくる幸せをひたすら待ちつづけるという能力は、決して侮れないものである。それはあたかも、われわれが論理性と呼んでいる思考法の卑小さをあざ笑うかのようにすら感じる。そして、おそらくこうした世界観や価値判断は彼らが離島で生きていくにあたって十分に有用で適応的なものだったのだろう。
■やみくもに神秘化し異質化するつもりはないのだが、フィールドにいるとメラネシア的心性としかいいようのないものにしばしば直面する。貨物船の漂着という事件から海の向こうの千年王国を創造する論理的飛躍(われわれからみればそういわざるを得ない)が、たとえばかれらがもつ全的理解の能力にどこか関わりがあるのではないかと、そんなふうに考えてしまうのだ。
| New▲ ▼Old |